加熱時に試験管の口を下に向ける理由
- 善ちゃん

- 2024年3月20日
- 読了時間: 4分
化学実験は正しく行うと実に楽しいです。
それは、個人的に、個人的なレベルの実験において、計算した通りの結果が得られやすいからです。
ときに試験管に固体の薬品を入れて加熱する実験がありますが、必ず試験管の口を下向きにしなければなりません。
何故でしょう?
加熱すれば、固体は溶けて先端の方へ流れ落ちてしまうのに矛盾しているのでは?

【某ガスの製法実験の様子(モノクロ画像)】
ここでは
と分けて解説しています。
【試験管で固体を熱する時、管の口の方下げる理由】
試験管を加熱する際に使うアルコールランプでも1,000℃以上、ガスバーナーでは1,500℃と炎は非常に高温です。
試験管のその火に触れる部分は非常に高温になります。
そこで、簡単に理由を言えば、混合の固体物には水分が含まれていて(例えば水和物、また化学反応時に水は発生する等)、熱することで試験管内で水蒸気が発生し、試験管を上向きにしていると、その水滴が熱している部分に流れて、試験官が割れてしまう恐れがあるため、試験管の口の方を下向きにするのです。
もう少し詳しく述べると以下のとおりです。
水の沸点は100℃です。
アルコールランプやガスバーナーで熱せられている箇所は1,000℃を超えます。
試験管の外側の加熱部分のガラスは膨張し、その箇所の内側に水が触れると冷やされ収縮します。
この温度差による膨張と冷却によって耐熱性があるガラスだとしても割れてしまうのです。
試験管が割れてしまい中の物質が溶け出たり、気体が漏れ出てしまうことの防止や試験官が割れない対策として、試験管の口の方を下向きにするのです。
また、下向きにしても、試験管の底の部分を加熱してしまうのもNGです。
と言うのは、加熱していくにつれ物質が固体から液体、液体から気体と変化していき、底の方から大きな気泡が発生し沸騰した液体が押し出されて、試験管から勢いよく噴き出してしまう(これを突沸と言います)ため、斜めにすることで気泡に対して押し出す直径を大きくしておくことで、押し上げる液体の量、液体にかかる圧力を小さくできるのです。
言うまでもありませんが、いきなり試験管に火を当て続けるのではなく、少しずつ火を当てて徐々にガラスを温めてから、火を当て続けて加熱します。

【この画像で登場する理科機器の名前】

【パイトーチ】
パイトーチはアルコールランプよりカロリーが高く、また芯が燃え尽きてしまうこともなく使い勝手が良く気に入っています。画像では2芯を使っていますが、取替用で1芯もあり2パターンですが火力調節もできます。
【レトルト台】
実験台より廉価で購入でき、ちょっとした実験では使い易いです。
【試験管】
試験管はこうした熱変化をする場合、耐熱ガラス製を使用します。一般的にPyrex(パイレックス)とするされたものです。パイレックスはアメリカの大手ガラス製造メーカー・コーニング社で生産・販売されていましたが、今はメーカー廃盤となっていて、耐熱ガラスのことをパイレックスと呼んでいます。パイレックスはガラスの熱の王様と言う意味です。
【最後に】
化学実験には危険が付きものです。
でも、それは日常生活を過ごすことでも考えてみると危険がたくさんあるのと同じものなのです。
正しく取り扱い、そして正しく実験方法を確認して行えば、目近で正しい解答・真実を得られ、目近で貴重な体験ができ、何より安全を知ることができるのです。
安全性、そして化学変化・化学反応も含めた薬品の取扱いや実験の知識や経験を確立し、そこに「なぜ、この実験を行うのか」と言う意義と言った科学リテラシーも、しっかり持って臨むことができます。
目の前で起きる実験は画面から見られるモノとは全くの別物で、音、熱、風等を体感でき、迫力も断然異なります。
科学実験を見よう、やろう!
感動こそが原動力!
多くの子どもたちにが科学技術に憧れと夢を持ってくれますように。
そして、日ごろからの生活を科学的に考えられる科学脳を養おう!
と願いを込めて。
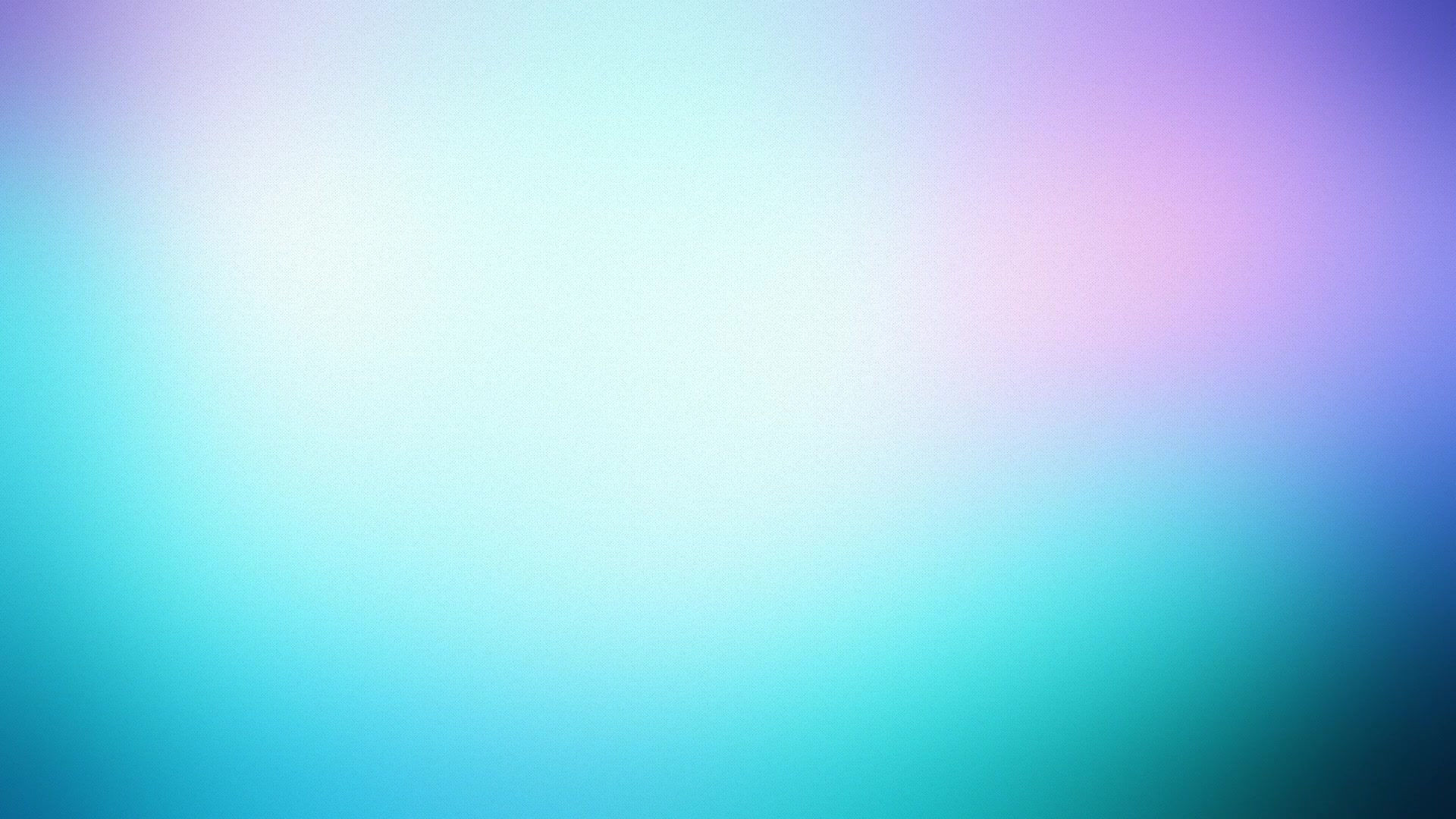







コメント